[総合案内]分析の型をつくる実行支援パートナー
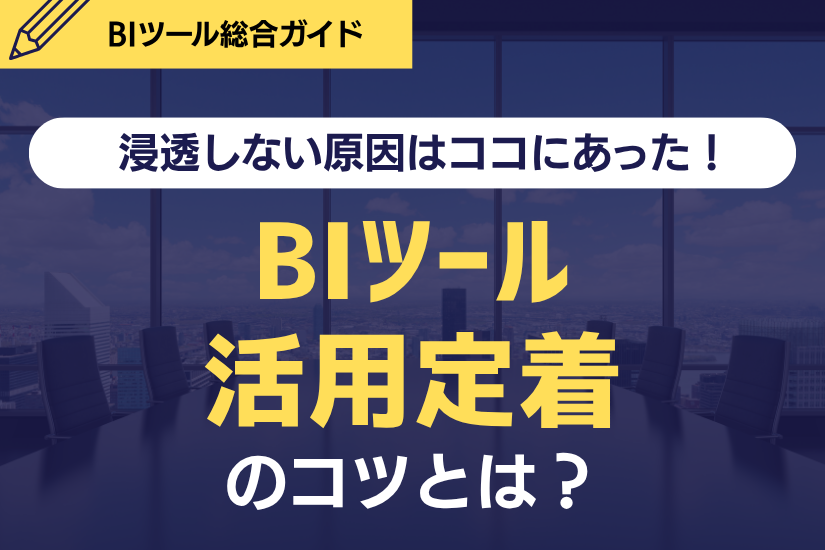
更新日:2025.10.30
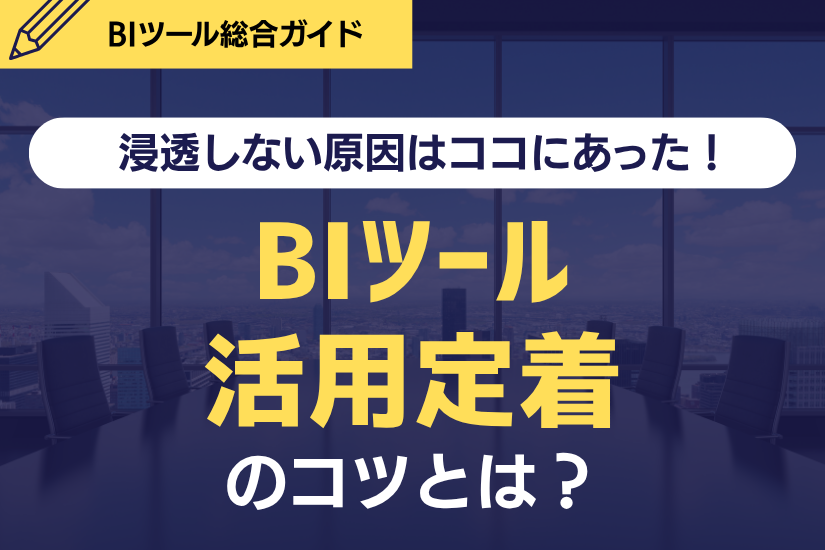
目次
近年、多くの企業がBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入しています。しかし「ダッシュボードを作ったのに見られない」「一部の人しか活用していない」「定着せずに形骸化してしまった」といった声も少なくありません。
なぜBIは思ったように浸透しないのでしょうか?
今回はその原因と、現場に定着させるためのコツを、現場伴走を得意とするデータ女子の視点から解説します。
![[総合案内]分析の型をつくる実行支援パートナー](https://datascience.cocoo.co.jp/hs-fs/hubfs/DS/img/wpdl/cocoo_data_service_2024_v1.png?width=1920&height=1080&name=cocoo_data_service_2024_v1.png)
[総合案内]分析の型をつくる実行支援パートナー
「せっかくBIを導入したのに、誰も見ていない…」
「一部の人しか活用しておらず、結局Excelに戻ってしまった…」
そんな悩みは、多くの企業が直面しています。BIが浸透しないのは「ツールが悪いから」ではなく、導入や運用のプロセスに共通する落とし穴があるからです。ここでは、よくある3つの原因を整理してみましょう。
.png?width=1920&height=600&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(29).png)
BIツールを導入すると「これでデータ活用ができる!」と安心してしまう企業は少なくありません。ところが実際には、導入しただけでは何も変わらないのが現実です。導入をゴールにしてしまうと、現場では「結局、何を見ればいいの?」「この画面は誰のためのもの?」と混乱が生まれ、活用が進まなくなります。
特にシステム部門主導で導入した場合、現場の課題や目的が共有されないままプロジェクトが進みやすく、完成したダッシュボードが“誰も開かない置物”になってしまうケースも。
BIはあくまで「業務改善や意思決定を助けるための道具」であり、ツール導入はスタート地点にすぎません。
.png?width=825&height=258&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(30).png)
「数字は出ているけれど、正直よくわからない」――現場ユーザーからこんな声が上がることも多いです。
せっかく最新のBIを導入しても、ダッシュボードの設計が複雑すぎると利用は定着しません。項目が多すぎたり、専門用語や略語が並んだりすると、数字を見る前に“理解のハードル”が立ちはだかります。
特にExcelや紙のレポート文化に慣れている現場にとって、突然「おしゃれだけど複雑な可視化」を提示されても、すぐには馴染めません。これでは「見るのに時間がかかる」→「開かなくなる」→「浸透しない」という悪循環に陥ります。
解決のヒント
まずは“シンプルさ”を重視しましょう。指標は3~5個程度に絞り、色や単位のルールを統一するだけでも、理解度が一気に上がります。小さな「見やすい!」体験が、BIを使い続けるきっかけになります。
.png?width=825&height=258&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(31).png)
BI浸透の最大のポイントは“人”です。どんなに高性能なツールを導入しても、日々の業務や会議に自然に組み込まれなければ定着しません。例えば「毎週の営業会議で必ずBIを開く」「KPI進捗は紙ではなくBIで確認する」といったルールや習慣がなければ、利用は一部の担当者に限定され、属人化してしまいます。
また、担当者が異動・退職すると運用が途切れてしまうのもよくある失敗です。運用が“人任せ”になっていると、いつの間にか活用されなくなり、投資が無駄になってしまいます。
解決のヒント
BIを“チーム全体の仕組み”に組み込むことが大切です。誰が見ても同じように理解できる設計、会議で必ず開く習慣、ルール化された更新サイクル。こうした仕組みを整えることで、BIは特定の人だけでなく組織全体に根づいていきます。
BIを導入しただけでは成果は生まれません。大切なのは「どう運用し、現場に根づかせるか」です。
ここからは、実際の現場でBIを“使われるツール”に変えていくための具体的なコツを紹介します。
BIを全社で一気に広げようとすると「複雑すぎて使われない」「現場がついてこない」といった失敗が起きがちです。最初は範囲を絞り、例えば営業部で「受注率を追いやすくなった」「商談の優先順位を決めやすくなった」といった小さな成功体験をつくることが大切です。
現場に「BIを使うと便利だ」という実感が生まれれば、自然と他部門にも広がっていきます。
これは“草の根的な浸透”の一番の近道です。
BIは作って終わりにしてしまうと、どうしても形骸化します。現場から「このグラフは色を変えたほうがいい」「数字より推移を見たい」といった声が上がったら、可能な範囲で改善していきましょう。
この“改善サイクル”を回すことで、ダッシュボードは使う人に合わせて進化していきます。現場にとって「自分たちの声が反映されるBI」になれば、活用モチベーションはぐっと上がります。
BIは“見るもの”ではなく“使うもの”にしなければ定着しません。例えば…
このように日々の業務フローに“BIを必ず通る仕組み”をつくれば、自然に活用が根づきます。
BIは単なる可視化ツールではなく、データに基づいた意思決定の文化をつくる存在です。経営層やマネージャーが率先して「その根拠はBIで確認した?」と問いかけるだけでも、データを見る習慣が広がります。
また、現場メンバーが数字を使って会話できるようにする教育も重要です。数値の意味を解説した“簡易ガイド”を添えたり、朝礼でBIを共有するだけでも「データで話す」文化は少しずつ根づきます。
自社だけで定着させるのが難しいと感じたら、外部の支援を活用するのも一つの手です。特に“現場と同じ目線で課題を整理してくれる伴走型の人材”が入ると、ツール導入から運用までスムーズに進みます。
データを専門に扱う外部人材が「この項目は不要では?」「このグラフは会議用にもっとシンプルに」とアドバイスするだけでも、BIの活用度は大きく変わります。
BIが浸透しない背景には「目的の不明確さ」「見づらい設計」「運用習慣の欠如」といった要因があります。逆にいえば、小さな成功を積み上げ、現場の声を反映し、データ文化を育てることが活用定着の近道です。
データ女子から一言
私たちデータ女子は、BI導入のゴールを「ダッシュボードを作ること」ではなく「現場に使い続けてもらうこと」と考えています。現場の小さな“困った”を拾いながら、伴走型で改善を重ねることで、BIが“仕事の一部”として根づいていきます。
「BIを導入したけれど思うように活用できていない…」と感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。