[案内資料]BIツール導入支援パック
解決のヒント
✔ 定期的なモニタリングや監査を行い、ルールの遵守状況をチェックする
✔ 現場の声を反映させ、使いづらいルールは見直す
✔ KPIを設定し「遵守率」「入力精度」などを可視化することで改善サイクルを回す
更新日:2025.09.30
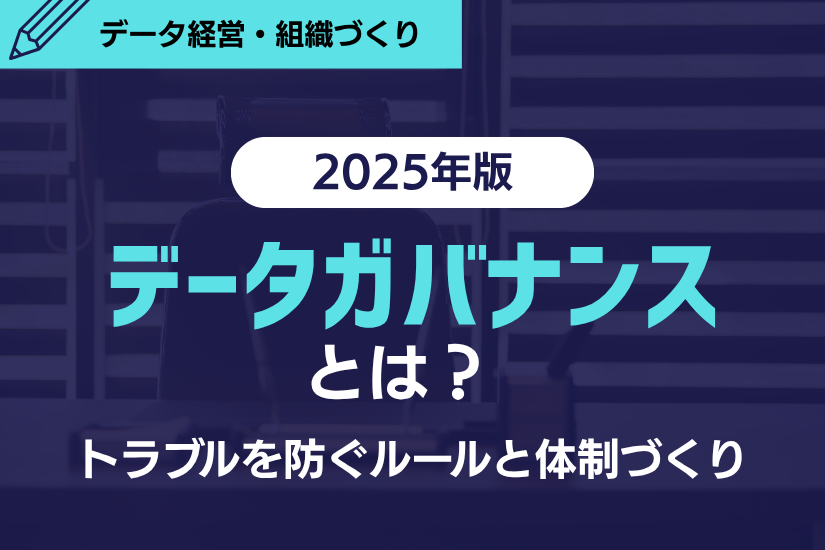
目次
近年、企業が扱うデータの量は爆発的に増加しています。生成AIやBIツールの普及により、誰もがデータを扱えるようになった一方で、誤用や漏洩などのリスクも急増しています。
こうした時代に欠かせないのが「データガバナンス」です。単なるルール作りではなく、企業全体でデータを安全かつ有効に活用するための「体制づくり」が求められています。
本記事では、2025年版データガバナンスの最新動向を踏まえながら、基本的な定義から実践ステップ、導入事例までを解説します。

[案内資料]BIツール導入支援パック
データガバナンスとは、組織全体でデータを安全かつ効率的に利用するための仕組み・ルール・体制を指します。似た言葉に「データマネジメント」がありますが、違いは次の通りです。
データマネジメント:データの収集・保管・活用といった「運用管理」そのもの
データガバナンス:その運用を正しく導くための「ルール・体制」
つまり、マネジメントが「実務」だとすれば、ガバナンスは「方針と統制」です。
データガバナンスは、ここ数年で急速に注目を集めるテーマとなりました。
その理由は単なる流行ではなく、社会的・技術的な背景があるからです。以下の3つは特に大きな要因です。
法規制の強化
個人情報保護法やGDPRをはじめ、国内外でデータ関連の規制が年々厳格化しています。
違反すれば多額の制裁金やブランド毀損につながります。
生成AIの普及
社員が気軽にAIツールにデータを入力する時代。
機密情報が外部に流出するリスクが現実的になっています。
データ活用の高度化
BIツールやデータ分析が一般化し、現場部門でもデータ活用が進んでいます。
だれもが扱えるからこそ「品質やルールのばらつき」が課題になりやすいのです。
データガバナンスを導入すると、単にトラブルを防ぐだけでなく、組織全体の競争力向上につながります。
ここでは代表的なメリットを7つに整理しました。
誤ったデータ入力や重複データの登録は、意思決定の誤りにつながります。
データガバナンスを徹底することで、データの取り扱いが標準化され、ヒューマンエラーや情報漏洩などのリスクを大幅に減らすことができます。
「正しいデータが、正しい形で、正しいタイミングに存在する」状態を作れるのが最大の効果です。品質の高いデータは、営業活動やマーケティング施策の成果を高め、経営会議での意思決定を迅速かつ的確にします。
国内外で厳格化が進むデータ関連法規制(個人情報保護法、GDPRなど)に対応しやすくなります。
さらに、監査や内部統制の際に「誰がどのデータをどのように扱っているか」を説明できるため、監査対応のコスト削減にもつながります。
各部門でバラバラに管理していたデータを統一できることで、データ探索や修正の時間を削減できます。
データクリーニングやレポート作成の手作業も減るため、担当者は付加価値の高い業務に集中でき、結果的に人件費やシステム維持コストの最適化につながります。
信頼できるデータが整理されている状態では、分析やBIツールの導入効果が最大化されます。
「データを探す・確認する」といった前処理の時間を短縮でき、現場が迅速に施策を回せるようになります。
データガバナンスの枠組みを整えることで、社員が「安心してデータを活用できる」環境が生まれます。
属人的な判断に頼るのではなく、データを根拠にした意思決定が文化として根づくため、組織全体のデータリテラシーも底上げされます。
企業がデータドリブン経営を進めるうえで、データガバナンスは土台となる存在です。
正しいデータ活用が定着すれば、顧客体験の改善、新規事業の立ち上げ、株主・投資家からの信頼獲得など、長期的な企業価値の向上にも直結します。
データガバナンスは「何を決めるか」と同じくらい「誰がどう運用するか」が重要です。
そこで、基本的な構成要素を整理しておきましょう。
データポリシー
利用目的や定義、禁止事項などを明文化
データ品質管理
正確性・一貫性・最新性を保つ仕組み
セキュリティと権限管理
誰がどのデータにアクセスできるかを明確化
組織体制(データガバナンス委員会など)
経営層から現場までを巻き込み、責任者を明確にする
教育・浸透活動
社員にルールを理解してもらい、日常業務に定着させる
導入といっても、いきなり完璧な体制を作る必要はありません。
段階的に整備していくことが現実的で、定着しやすい方法です。
以下では5つのステップを紹介します。
✔ どの部署でどんなデータが扱われているか棚卸し
✔ データ管理上のリスクを洗い出す
✔ 経営戦略と連動させたデータ活用の方向性を決定
✔ ポリシー文書を作成
✔ データオーナーやデータスチュワードを任命
✔ ガバナンス委員会を設置
✔ データ定義書や利用マニュアルを作成
✔ 権限設計を実施
✔ 研修やEラーニングで全社員に浸透
✔ 定期的にルールを見直し、改善を続ける
ある製造業の企業では、営業部門ごとに管理していた顧客データがバラバラで、重複登録や情報不足が頻発していました。そこでデータガバナンス体制を整備し、入力ルールを統一。さらにBIツールを導入し、営業・マーケティング・経営層が同じデータをリアルタイムで確認できるようにしました。
結果として、
✔ 顧客データの重複率が半分以下に
✔ 営業会議の準備時間を大幅短縮
✔ 経営層の意思決定スピードが向上
といった効果が得られています。
データガバナンスは重要である一方、導入や定着の過程ではさまざまな課題が生じます。
ここでは、企業が直面しやすい代表的な課題と、その解決のヒントを整理します。
課題
ポリシーやマニュアルを作成しても、現場に浸透せず「形だけのガイドライン」になってしまうケースが多く見られます。時間が経つと運用がルーズになり、当初の目的が忘れ去られることもあります。
解決のヒント
✔ 定期的なモニタリングや監査を行い、ルールの遵守状況をチェックする
✔ 現場の声を反映させ、使いづらいルールは見直す
✔ KPIを設定し「遵守率」「入力精度」などを可視化することで改善サイクルを回す
課題
営業やマーケティング部門では「入力ルールが増えて業務負担が増える」と感じる社員も少なくありません。
結果として、データ入力が後回しにされ、品質低下を招きます。
解決のヒント
✔ 入力負担を減らす仕組みを用意(自動入力やシステム連携)
✔ なぜルールが必要かを具体的に説明し、現場に納得感を与える
✔ 正しく入力したデータが営業活動や評価にどう役立つかを示し、「自分ごと化」させる
課題
データガバナンスを推進するには、データの扱いに長けた人材が必要ですが、多くの企業では人材不足が現実です。IT部門に丸投げすると、現場の業務理解が不十分なまま形骸化するリスクもあります。
解決のヒント
✔ 外部の専門家や伴走型サービスを活用し、社内の知見を育てながら進める
✔ データオーナー・データスチュワードといった役割を社内で明確化し、徐々に知識を蓄積する
✔ 研修や社内コミュニティを通じて「市民データサイエンティスト」を育成する
課題
データは複数部門にまたがって存在するため、縦割りのままでは整合性がとれません。
「自部署だけ正しく管理していればいい」という意識が残り、全社最適が進まないケースがあります。
解決のヒント
✔ 経営層のコミットメントを得て「全社横断のプロジェクト」と位置付ける
✔ データガバナンス委員会を設置し、部門横断でルールを策定する
✔ 共通のデータカタログや用語辞書を作り、認識のずれを解消する
課題
ルールを定めても、それに対応できるシステム環境が整っていない場合があります。
例えば、既存の基幹システムやCRMがルールに対応しておらず、結局「運用でカバー」することに。
解決のヒント
✔ 新規システム導入時には必ずガバナンス要件を盛り込む
✔ 現行システムに機能不足がある場合はRPAや補助ツールでカバー
✔ IT部門と業務部門が共同で「現実的に運用できる仕組み」を検討する
課題
導入初期は盛り上がっても、担当者の異動や経営層の関心低下で徐々に失速してしまうことがあります。
結果として、「一度整備したけど今は使われていない」状態に陥ることも。
解決のヒント
✔ ガバナンスを「一度きりのプロジェクト」ではなく「継続的な取り組み」と定義する
✔ 年次計画に組み込み、定期レビューを必ず実施する
✔ 成果を定量的に示し、経営層に「投資対効果」を継続的に報告する
データガバナンスが失敗する大きな原因は「ルールを作って終わり」にしてしまうことです。
解決のヒントは「現場に寄り添い、小さな改善を繰り返し、経営層の支援を得ること」。
これにより、データガバナンスは形骸化せず、組織文化として定着していきます。
データ女子から一言
データガバナンスを実現するには、ルールだけでなく「現場にどう浸透させるか」がカギとなります。
私たち「データ女子」は、現場に寄り添いながら小さな改善を積み重ね、データ活用を「文化」として根づかせるお手伝いをしています。
